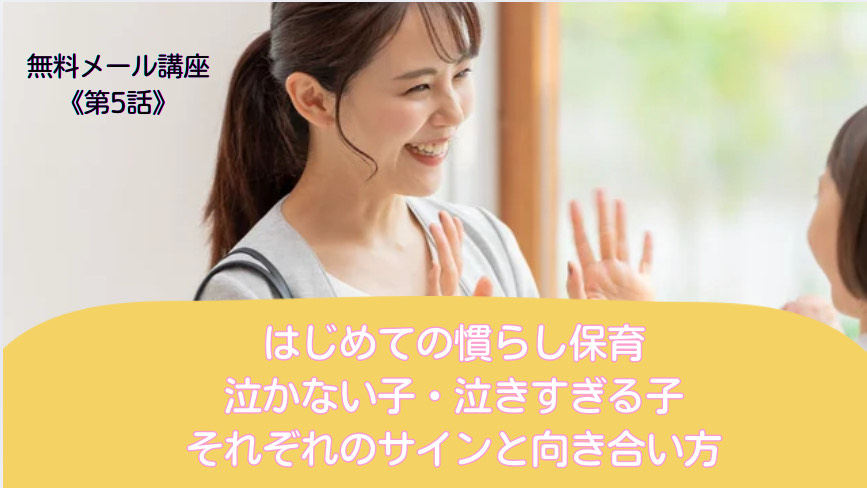慣らし保育で【泣かない子】と【退園を考えるほど泣く子】の理由とママができる9つのこと
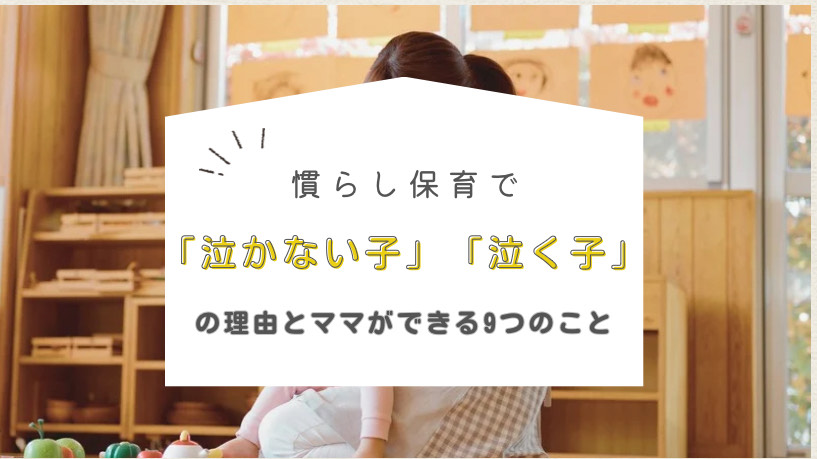
0歳1歳2歳で保育園に子どもを預けると、
【目次】
- 慣らし保育ってなんでするの?期間はどのぐらい?
- 慣らし保育で泣かないのは、愛情不足や発達障害が問題? ~具体的な5つのタイプ~
- 退園を考えるほど、
なかなか子どもが慣れないのは、甘やかしすぎ?園が悪い? ~5つの要因~ - 預けはじめに多い、SIDS(乳幼児突然死症候群)が怖い ~預けはじめが重要。ストレスが大きな要因の1つ~
- 家庭での様子が、子どもの【本音】~家庭での見守りチェックポイント~
- 子どもが保育園で安心して過ごすために ~ママができる9つのこと~
- 自分の心配やしんどさを誰も分かってくれないと感じる時は
慣らし保育ってなんでするの?期間はどのぐらい?
赤ちゃんにとって、ママは世界のすべて。いつもそばにいて、
また、保育園生活は、
一般的な目安は、1週間〜2週間ですが、体調や性格、
慣らし保育がはじまると、園の様子が少しずつ見えてきたり、
「うちの子だけ、全然慣れなくて、ご飯も食べず、お昼寝もせず、
「他の子は泣いているのに、うちの子は全然泣かない。大丈夫なのかな?」
「保育園での突然死が多いときいて、
いきなり長時間離れることは、
時間をかけて、子どもは、保育園の環境や保育士さん・お友だちに慣れ、ママは、仕事の環境や送迎・家事の段取りに慣れていくことで、
慣らし保育で泣かないのは、愛情不足や発達障害が問題?
慣らし保育で泣かない子どもは一見「順応が早い」「強い子」と思われがちですが、とても繊細で大切なテーマです。
「発達障害があるかもしれない」
「愛情不足が原因かもしれない」
多くのママが、子どもが泣かないことで不安になる2つの背景を詳しくみていきましょう。
具体的な5つのタイプ
0〜3歳で発達障害の診断をつけることは極めて難しく、先天的な障がいでないかぎり「
大切なのは、「発達障害」「発達障害ではない」
どのお子さんでも(大人でも)、
1. 情緒表出が控えめな子(内向的・抑制的な気質)
慣れるまでに時間がかかるタイプで、環境に“凍りつき”
- 初対面の人や新しい環境で感情を表に出しにくい。
- 怖くても固まってしまい、泣かずに黙って観察する。
- 1、2ヶ月後に泣き出す可能性がある。
2. 視覚・聴覚などの感覚が鈍感な子(感覚鈍麻タイプ)
環境の変化やストレスに自分で気づきにくいため、
- 周囲の変化に対して反応が薄い。
- 大きな音や賑やかな場所でも平気なように見える。
- 体調をよく崩す
3. 対人関係への関心が薄い子(社会的関心の低さ)
人とコミュニケーションが取ろうとせず、
- 保育者や他の子どもとのやりとりにあまり関心を示さない。
- 一人遊びを好み、周囲と関係を築こうとしない。
4. 非常に順応性が高い子
気質的に非常に“合わせ上手”な子。
• 環境の変化に柔軟に対応。周囲を観察し、
• 家に帰ってから不機嫌になったり、夜泣き・癇癪が増えるなど「
5. 不安を外に出せない(表出が難しい)子
情緒的に抑制的、もしくは身体の機能的問題で、
- 急に不機嫌になったり、癇癪が増えるなど「反動」が出る。
- よく体調を崩す。
5つのタイプを参考に、
- 子どもが困っているか、困っていないか
- どんな事に困っているか
2点を注意深く観察し、子どもが困っていそうであれば、困る原因になっていることに対しての早急な対応が必要です。具体的な姿を先生に共有して協力を仰ぎましょう。
子どもは困ってなさそうでも、
預けても泣かなかった息子に甘えて、仕事を謳歌していたら、日常の中で息子の逆襲(自己主張)がじわじわとはじまっていました。気が付いたころには負のループに突入。慣らし保育「泣かない時期」と「しがみつく時期」危機一髪のような危険な状況を経て、変化していった親子関係の軌跡を綴っています。
↓↓↓↓↓
退園を考えるほど、なかなか子どもが慣れないのは、甘やかしすぎ?園が悪い?
園では
- ミルクや食事をとらない
- 寝ない
- 先生がずっと抱っこしてても泣いてる
家では
- 急に夜鳴きが始まった
- 外出するのを拒否する
- 大泣きして服も着替えない
- 赤ちゃん返りしてずっとひっついている
こんな姿が出ていたら、
子どもがなかなか慣れない理由は、子ども自身の特性・環境の問題・
なかなか慣れない子どもの5つの要因
1.子どもの気質と発達段階
- ママとの愛着が強く、
離れることに強い不安を感じる - 初めての集団・初めてのママ以外の大人との関わりで慣れるのに時間がかかる
- 自己調整(気持ちを切り替える力)がまだ育っていない
- ことばの理解がまだ不十分で、見通しがもてず、「なぜママがいないのか」
が理解できず不安になる - 他の子どもや大人と関わる経験が少なく、集団の中で緊張しやすく、どう関わればいいかわからない。
2. 保護者の不安が子どもに影響している
- 「泣いてるのに預けて大丈夫かな…」というママの園に対する心配が、
子どもに伝わっている - 先生に引き渡す時にママが心配で、離れるのが寂しい表情をしている
3.慣らし保育の進め方が子どもに合っていない
- ステップが急すぎる
- まだ環境に慣れていないのに、時間だけ先に延ばしてしまう
- 保育者との関係づくりが進まず、子どもにとって「安心できる大人」がまだいない
- 分離の時のお部屋や時間が一貫していない
- バイバイの仕方が毎日違ったり、
時にはこっそり離れたりしてしまう
4.体調・生活リズムが安定していない
- 睡眠不足・偏食・感染症などで体調が安定せず、
不機嫌になりやすい - 保育園に行くリズムが作れない(例:週に2~
3回しか行かないなど)
5.発達的な特性が関係している場合も
- 感覚に敏感(音・におい・人混みなど)で、園の環境や人の多さそのものに圧倒されて、落ち着けない
- 自分のやり方やペースに強いこだわりがあり、
それが崩れると不安定になる。 - 変化や新しいことを拒否しやすい
保育園との連携がカギ!
慣らし保育が長引く場合は、家庭で子どもが安心して登園できるために出来る限りのことはした上で、「子どものペースを尊重しつつ、
たとえば:
- 子どもの人数が多くなる前に少し前に登園して、担任の先生にゆったり受け入れてもらう
- のお部屋や仕方を毎回同じにする(安心のルーティン)
- 今日何して遊ぶか、視覚的に見通しが持ちやすいようにする
など、お家でできることと、園でしてもらえることを協力体制で進めるよう、先生との信頼関係を深めましょう。
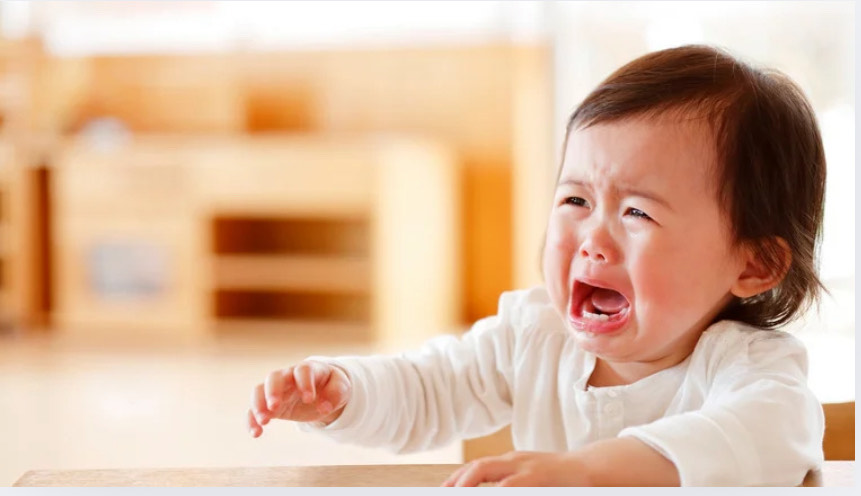
預けはじめに多い、SIDS(乳幼児突然死症候群)が怖い
ニュースなどで報道される保育園での事故は、預けることが不安になる要因の1つですね。感染症や転落、窒息など、乳幼児期に起こりやすい事故はいろいろありますが、予兆なく命に直結する乳幼児突然死(SIDS)は怖いですよね。原因はまだ明らかになっていませんが、世界で研究が進められています。様々な調査研究結果から、慣らし保育で発症のリスクを低くすることができるのはご存じですか?
突然死は1歳以上でも発症する
・SIDS(乳児突然死症候群)は、それまで元気だった赤ちゃんが、何の予兆や病歴のないまま、眠っている間に突然死亡してしまう、原因が分からない病気です。
・1歳未満の赤ちゃんの死亡原因としては、第5位となっています。
・発症するのは、乳児期の赤ちゃんに多いですが、まれに1歳以上でも発症することがあります。
・発症リスクを低くするには、①あおむけに寝かせる ②できるだけ母乳で育てる ③たばこはやめる
預け初めが重要。ストレスが大きな要因の1つ
・預かり初期の乳児の疲労や環境変化に伴うストレスがSIDS発症に関与している可能性が考えられる。
・スウェーデンの報告で、若い両親が乳児を連れて旅行やアウトドア活動を行う機会が多くなり、家庭以外でのSIDS発症例が増加していることが報告されている
→赤ちゃんが知らない間に疲労がたまりSIDS発症リスクが高まる・アメリカ小児科学会では、預かり始めの一週間でSIDS発症の3分の1、さらにその2分の1が預かった初日であったことが報告
・わが国においては保育施設のSIDSに関する大がかりな調査報告はないが、保育環境における突然死の調査、分析を行った資料
→保育所で預かり初めの多くなる4月に最も多いと報告・発見時うつ伏せ寝だった児が6割を超えていた。このことからうつ伏せ寝とSIDSは保育環境においても強い相関が疑われる。
・発症当日に体調が良くなかった児が67.7%。体調不良の内容は保育の許容範囲(咳や鼻水など軽い風邪症状、食欲がない、機嫌が悪い、何となくいつもと様子が違う等)であり、SIDSのような深刻な結果を想像しがたいぐらいの体調不良
この他にも、「母親と離れた環境での睡眠時の脳波」に関する研究は、発達心理学や神経科学の分野でいくつか行われており、赤ちゃんんの情緒の安定や睡眠の質に影響する可能性が示されています。
慣らし保育は、命を守るためにも大切なステップ
・預かり初期の発症が多いことを認識し、子どもの体調や様子を見ながら時間をかけて、無理ない進め方を心がけることが、最も大きな事故予防になります。
・毎朝の体調把握、特に「いつもと違う」様子に注意を払いましょう。
・園での対策について聞いておきましょう

家庭での様子が、子どもの【本音】
「泣く」「泣かない」園で出す姿は様々ですが、
おうちで見せる変化が、子どもの『本音』
家庭での見守りチェックポイント
※週1回〜数日ごとに確認するのがおすすめです。
身体や生活の変化
☐ 夜泣き・夜中に起きることが増えた
☐ 食欲が落ちてきた/食べる量が極端に変わった
☐ 排泄が不安定(おもらし、便秘、頻尿など)
☐ 熱や腹痛など、体調不良が続いている
☐ 疲れているように見える/寝ても疲れが取れていない様子
感情・行動の変化
☐ 家でよく癇癪(かんしゃく)を起こすようになった
☐ 些細なことで怒る、泣くようになった
☐ よく甘えてくる、常に抱っこや付き添いを求める
☐ いつもより静か、笑顔が減ったように感じる
☐ 同じ遊びや行動を繰り返す(こだわり行動)
会話やコミュニケーションの変化
☐ 園でのことを聞いても話したがらない/「わからない」
☐ 表情が乏しくなったり、目を合わせなくなった
☐ 一人で遊びたがることが増えた
☐ 遊びながら突然泣いたり怒ったりする
【合計チェック数と対応目安】
- 0~2個:今のところ大きな変化は見られませんが、
引き続き様子を見守ってください。 - 3~5個:やや負担を感じているサイン。
園に家庭の様子を共有しましょう。 - 6個以上:強いストレス反応の可能性あり。
保育士や支援機関への相談を検討してください。

子どもが保育園で安心して過ごすために
「泣かない」子どもも、「泣く」子どもも、新しい環境に慣れ、
慣らし保育期間中、そしてその後も、
大事なのは「泣く・泣かない」ではなく「安心できているか」です。
家庭でママができるサポートは「安心感の積み重ね」です。安心できる時間+見通しある習慣+小さな分離の練習が、保育園に慣れるための土台になります。
家庭では思いっきり甘えたり、崩れたり、
赤ちゃんは話せなくても色んなことを理解しています。分からないと思わずに、丁寧に伝えてあげてくださいね。
ママができる9つのこと
1.スキンシップをたっぷり
抱っこ、おんぶ、目を見て話しかける、手をつなぐなど、肌と肌、心と心が通じ合う時間を1日10分!出発前、お風呂上りや寝る前のふれあい遊びやベビーマッサージもgood!
2.反応的な関り
泣いたり、訴えたりしたときにすぐに応えてあげる。「分かってもらえている」という実感が、安心感につながります。
3.毎日同じ流れで過ごす(リズムある生活づくり)
起きる→朝ごはん→着替える→出…と一定のパターンにすると、子ども自身が見通しを持ちやすくなり安心して過ごせます。
4.笑顔で見送る・迎えに行く
別れ際と再会を大切に。「行ってらしゃい」「お迎えにくるよ」「おかえり」「会いたかったよ!」毎日、同じ言葉を明るく繰り返すことで安心感がでます。リアクションを大きめに声
をかけてあげましょう。
5.園での遊びを共有する
保育園でのお便りや先生との会話からの情報、子どもが新しく楽しんでいる遊びや会話からイメージを広げて、保育園で楽しんでいる歌や遊びを家でも一緒に楽しむことが、園での時間
もママとの楽しい時間を思い出し安心に繋がります。次の日の予定を伝えてあげることも、見通しをもてて安心につながります。
6.話したくなる時間
こちらから園での様子を色々聴くよりも、
間など、ママの気持ちをゆったりもつ時間をつくってみてください。
7.寝る前の10分を大切に
一緒にお布団にはいり、心と身体を子どもに向ける時間を作りましょう。安心できる声で語りかけてあげることは、
すり眠れることで、免疫力を高め、
8.楽しい分離を生活の中でちょっとずつ
「ママ、トイレいってきま~す!」戻ったら「ただいま~!」と短時間離れる時間を遊びのような感覚で楽しむ。パパや祖父母とのお留守番など、こっそり離れず、バイバイの体験の積
み重ねが、ママと離れていても楽しい時間がある、ママは必ず帰ってくるという見通しがもてるようになります。
9.ママ自身の心の安定が大事
ママが安心して送り出せると、子どもにも伝わります。不安なときは、先生とこまめにコミュニケーションをとりましょう。ママ自身がリラックスする時間を持つことも大切です。

自分の心配やしんどさを誰も分かってくれないと感じる時は
園での姿と家庭での姿がかけ離れていると、ママの心配を「
家庭内でも、
焦らなくて大丈夫。慣らし保育の期間や慣れるまでの時間、出す姿は、
「うちの子は…」と周りの子どもと比べて焦る必要はありません。
子どもを預けて仕事をすることは、
大事なことは、「あなたは大切な存在だよ」「
ママは、子どもが生まれてきてから1番長い時間を過ごしている、
そして、諦めず、根気強く関わり続けてくださいね。
更に詳しく、具体的な声掛けや関り方、遊びの提案なども含めた内容をメール講座にしました。
はじめての慣らし保育で、子どもの姿に不安を感じたり、悩んだ時に、力を抜いて子どもを見守る、関わることができるきっかけになれば幸いです。
↓↓↓↓↓